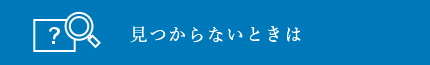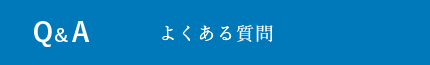本文
国民年金(基礎年金)について
国民年金は、国籍に関わらず、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。
| 1 国民年金の種別・届出 |
| 2 国民年金の保険料 |
| 3 国民年金の免除制度と追納制度 |
| 4 国民年金の給付 |
| 5 年金を増やしたい人へ(任意加入、付加年金、国民年金基金) |
| 6 マイナポータルを利用した国民年金に関する電子申請 |
| 7 公的年金シミュレーター(試験運用中) |
年金に関するお問い合わせやお手続きは、出張年金相談やお近くの年金事務所でも可能です。
【出張年金相談のご利用について】
一関年金事務所による出張年金相談を、市役所で開催してします。
開催日および会場
※ 開催日および会場は現時点の予定です。今後変更・中止となる場合もあります。
| 開催日 | 会場 |
| 4月20日(木) | 大船渡市役所 第1会議室 |
| 5月25日(木) | |
| 6月22日(木) | |
| 7月27日(木) | |
| 8月10日(木) | |
| 9月28日(木) | |
| 10月26日(木) | |
| 11月30日(木) | |
| 12月21日(木) |
| 開催日 | 会場 |
| 1月25日(木) | 大船渡市役所 第1会議室 |
| 2月22日(木) | |
| 3月21日(木) |
時間
午前10時30分~午後3時30分
予約制
ご予約は相談日の1か月前から、一関年金事務所に電話でお申し込みください。
予約の際の確認事項
(1)氏名 (2)生年月日 (3)住所 (4)基礎年金番号 (5)連絡先の電話番号
(6)主な相談内容
定員になり次第受付終了となります。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止になる場合や、会場が変更になる場合があります。
予約受付・お問い合わせ先
一関年金事務所(☎0191-23-4246)
お近くの年金事務所をご利用される場合
| 所在地 | 〒021-8502 岩手県一関市五代町8-23 |
|---|---|
| 電話番号 | 0191-23-4246(自動音声でのご案内) |
| FAX番号 | 0191-31-1229 |
| 受付時間 | 平日は午前8時30分から午後5時15分まで(週初めの開所日は午後7時まで延長) 週末相談として、第2土曜日は午前9時30分から午後4時まで |
| 休業日 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日) |
事前に必ず予約をしてください。
- お申し込み先は、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)または年金事務所へ。
- 予約相談希望日の1か月前から前日まで受付しています。
- ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をご準備ください。
【不審な電話にご注意を!】
年金事務所や市役所の国民年金担当職員を装い電話をかけ、家族の勤務先や、電話番号、住所などの個人情報を聞き出すという不審な行為が市内でも発生しています。怪しいと感じたら、個人情報を話したり、現金を支払ったりせずに、年金事務所または市役所までご相談ください。
1 国民年金の種別・届出
【国民年金加入者(国民年金被保険者)の種別】
結婚、離婚、就職や退職などで被保険者の種別が変わる時は、お手続きが必要です。
第1号被保険者
20歳以上60歳未満の、自営業、農林漁業、フリーアルバイター、学生や無職の人
第2号被保険者
70歳未満の会社員や公務員(厚生年金保険料として、毎月の給料から引き去り)
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
(配偶者の加入する年金制度が保険料を負担するため、納付の必要はありません)
【国民年金の届出】
こんなときは届出をしてください。
| こんなとき | 届出に必要なもの | 届出先 |
|---|---|---|
| 退職したとき | 年金手帳または基礎年金番号通知書 退職日がわかる書類(離職票、健康保険資格喪失証明書など) |
住所地の市区町村役場 |
| 就職したとき | お勤め先にご確認ください | お勤め先 |
| 厚生年金加入中の配偶者に扶養されるようになったとき(結婚など) | 配偶者のお勤め先にご確認ください | 配偶者のお勤め先 |
| 厚生年金加入中の配偶者の扶養からはずれたとき(離婚、配偶者の退職、配偶者が65歳になったなど) | 年金手帳または基礎年金番号通知書 扶養からはずれた日がわかる書類(被扶養者資格喪失証明書など) |
住所地の市区町村役場 |
2 国民年金の保険料
1.保険料
令和5年度の保険料は、月額16,520円(定額)です。
- 保険料は月単位です。加入日が月の初日でも末日でも、1か月分の保険料を納めます。
- 毎月の保険料とあわせて付加保険料(月額400円)を納めると将来受け取る年金額が増やせます(詳しくは、「5 年金を増やしたい方へ」をご覧ください)。
- 国民年金保険料の納付額は、全額が社会保険料控除の対象です。年末調整や確定申告に必要となる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は毎年11月上旬に送付されます。(10月以降に、その年初めて納付された方は、翌年2月上旬に送付されます。)
2.納付期限
納付期限は翌月の末日です。(例 4月分は5月31日が納付期限)
- 納付期限を過ぎると、「未納」として納付督励などの対象になります。
- 納付期限を過ぎた場合でも、納付期限から2年間は送付された納付書で納めることができます。2年を過ぎると時効により納付できなくなりますので、お早めに納付してください。
- 保険料を未納のままにしておくと、将来の老齢基礎年金や万が一の時の障害年金、遺族年金を受け取ることができない場合があります。
3.納付方法
- 現金納付(納付書での支払い)
納付書を使用し、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納付してください(納付書裏面に取扱金融機関及びコンビニエンスストアが記載されています)。 - 口座振替
ご希望の場合は、金融機関の窓口、年金事務所、または住所地の国民年金担当窓口へお申込みください。 - クレジットカード納付
ご希望の場合は、お近くの年金事務所、または住所地の国民年金担当窓口へお申込みください。 - 電子納付
インターネットバンキング、モバイルバンキング、またはATMでもご利用いただけます。納付の際は、ご利用の金融機関にお問い合わせください。 - スマートフォンアプリ
納付書のバーコードを、スマートフォンアプリで読み取ることによって、電子決済ができます。スマホ決済の利用には、納付書と対応する決済アプリが必要となります。
スマートフォンアプリを使用して国民年金保険料を納付する方法の詳細は、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
4.保険料の割引制度(前納がお得です!)
保険料の前納(前払い)をすると、下の表のとおり割引を受けることができます。口座振替による2年前納が、もっとも割引額が大きくお得です。なお、金額は年度ごとに変わります。
| 納付方法 | 1か月分 | 6か月分 (前期・後期) |
1年分 | 2年分 |
|---|---|---|---|---|
| 口座振替 | 16,470円 (50円) ※早割り |
97,990円 (1,130円) |
194,090円 (4,150円) |
385,900円 (16,100円) |
| クレジットカード 納付書 |
― | 98,310円 (810円) |
194,720円 (3,520円) |
387,170円 (14,830円) |
カッコ内は割引額
【納付書(現金)による前納の注意点】
- 2年前納は、4月初旬までに、年金事務所または住所地の国民年金担当窓口にお申し込みください。後日、2年前納用納付書が郵送されます。
- 1年前納や6か月前納用納付書は、4月に届く毎月支払い用納付書と同封されています。
- 年度途中に国民年金に加入した人は、加入月以降から令和6年3月末または令和7年3月末までの分を前納すると、月数に応じて割引が受けられます。年金事務所または住所地の国民年金担当窓口にお申し込みください。
【口座振替及びクレジットカードによる前納の注意点】
2年、1年、6か月(前期4月から9月分)前納は、2月末までに年金事務所または住所地の国民年金担当窓口にお申し込みください(後期10月から翌年3月分は8月末まで)。
3 国民年金の免除制度と追納制度
【免除制度】
保険料を納めることが経済的に難しい場合、ご本人が申請し、承認された場合に保険料の納付が免除または猶予される制度です。住所地の国民年金担当窓口、または年金事務所にご相談ください。
1.免除申請と納付猶予申請
申請期間は、7月から翌年6月までの分で、原則、毎年7月以降に申請が必要です(全額免除または納付猶予が承認され、翌年度以降も同じ免除区分での継続申請を希望した人を除く)。
過去の期間については、申請する月から2年1か月前までの分を申請できます。
(例)令和5年4月に申請できる期間:2年1か月前である令和3年3月分から
- 免除申請(全額免除・一部免除)
本人、配偶者(別居中を含む)、世帯主それぞれの前年所得が一定以下の場合や、失業などの事由がある場合、保険料が全額または一部免除(4分の3、半額、4分の1)となります。免除された場合、将来受け取る年金額は免除の種類によって減額されますが、年金受給資格期間(原則として10年以上)に含まれます。
※一部免除は、減額された保険料を納めないと未納となり、年金受給額の計算及び年金受給資格期間に含まれません。 - 納付猶予申請(50歳未満の人が対象)
本人、配偶者(別居中を含む)それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業などの事由がある場合、保険料の納付が猶予されます。猶予された場合、年金受給額には反映されませんが、年金受給資格期間(原則として10年以上)に含まれます。
(※平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象です。)
※納める金額は令和5年度月額(令和5年4月からの免除期間を納付する場合)免除の種類 納める金額 年金受給額への反映
(全額納付を1とした場合の比較)全額免除
(保険料全額を免除)0円 1/2 納付猶予
(保険料の全額が猶予)0円 なし 4分の3免除
(保険料の4分の1納付)4,130円 5/8 半額免除
(保険料の半額を納付)8,260円 6/8 4分の1免除
(保険料の4分の3納付)12,390円 7/8
(免除及び納付猶予申請の申請年度)
令和2年度分(令和2年7月から令和3年6月)
令和3年度分(令和3年7月から令和4年6月)
令和4年度分(令和4年7月から令和5年6月)
令和5年度分(令和5年7月から令和6年6月)
| 世帯構成 | 全額免除 納付猶予 |
一部免除 | ||
| 3/4免除 | 半額免除 | 1/4免除 | ||
| 4人世帯 (夫婦、子ども2人) |
172万円 (257万円) |
202万円 (300万円) |
242万円 (357万円) |
282万円 (407万円) |
|
2人世帯 |
102万円 (157万円) |
126万円 (191万円) |
166万円 (248万円) |
206万円 (305万円) |
| 単身世帯 |
67万円 (122万円) |
88万円 (143万円) |
128万円 (194万円) |
168万円 (251万円) |
2.学生納付特例申請
本人の前年所得が一定額以下の場合、学生の間の保険料納付が猶予される制度です。
申請期間は4月から翌年3月までの分で、年度ごとに申請が必要です。
過去の期間については、申請する月を基準にして、2年1か月前までの分を申請できます。
※猶予になった期間は、年金額には反映されませんが、年金受給資格期間(原則として10年以上)に含まれます。
(学生納付特例申請の申請年度)
令和3年度分(令和3年4月から令和4年3月)
令和4年度分(令和4年4月から令和5年3月)
令和5年度分(令和5年4月から令和6年3月)
【追納制度】
免除または猶予になった期間は、10年以内にさかのぼって保険料を納めること【追納】ができます。これにより、将来受け取る年金額を増やすことができます。追納をご希望の場合は、年金事務所または住所地の国民年金担当窓口にご相談ください。免除された期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合、加算額を含めた納付が必要です。(令和5年度中に追納する場合、平成25年度から令和2年度分について加算額が生じます。)
※追納は古い月の分から納付してください。
【産前産後期間免除制度】
平成31年4月1日から、第1号被保険者(本人が国民年金保険料を納付している人)が出産した場合に、出産前後の一定期間〔出産予定月の前月(双子などの場合は3ヶ月前)から、出産予定月の翌々月まで〕の保険料が免除されることとなりました。出産予定月の6ヶ月前から、届出することが出来ます。
4 国民年金の給付
1.老齢基礎年金
令和5年度年額 795,000円(※20歳から60歳になるまでの40年間納めた場合の満額)
保険料を納めた期間などが10年以上(※平成29年8月から)あると、65歳から受け取ることができる年金です。
納めた期間には、免除や猶予制度を受けていた期間、厚生年金に加入していた期間及びその配偶者に扶養されていた(第3号被保険者)期間などを含みます。
※保険料を納めていない期間があると、減額されます。
繰上げ受給と繰下げ受給
原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以降いつからでも受けられます。ただし、65歳前に請求し受け取ると減額され(繰上げ受給)、66歳以降に請求し受け取ると増額されます(繰下げ受給)。どのくらい減額及び増額されるかは、請求する年や月によって決まっています。一度請求すると、一生涯にわたって決められた割合で減額及び増額され、取り消すことができません。
○ 繰上げの減額率 0.4~0.5パーセント/1カ月
○ 繰下げ増額率 0.7パーセント/1カ月
※繰下げできる年齢には上限があり、それ以降に請求しても年金額は増えません。
昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)⇒70歳まで
それ以外の方⇒75歳まで
繰上げ受給をすると次の制限があります
- 特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の定額部分が一部支給停止になります。
- 遺族厚生(共済)年金とは65歳まで選択になります。
- 障害基礎年金や寡婦年金は受けられません。
- 請求後は任意加入することや、過去に保険料の未納分があってもさかのぼって納付することができません。
2.障害基礎年金
令和5年度年額 障害等級1級 993,750円 2級 795,000円
国民年金加入中に病気やけがなどで障害が残ったときや、20歳前の事故やけがなどで一定の障害の状態(障害等級の1級または2級)になった場合に受け取ることができる年金です。
【年金が受けられる要件】
- 初診日(病気やけがで初めて医師の診断を受けた日)において国民年金の被保険者であること。または、60歳以上65歳未満で、国内に住所があること。
- 初診日の属する月の前々月までの全被保険者期間のうち、保険料を納付した期間と免除された期間を合わせて3分の2以上あること。または直近1年間に保険料の未納がないこと(特例)。
- 初診日が20歳前であること(納付要件はありませんが、本人の所得制限があります)。
- 1.及び2.を満たした人、または3.に該当する人が障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)に障害等級の1級または2級に該当していること。
※障害年金の障害等級は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の等級とは異なります。
※障害基礎年金を受給する人に生計を維持されている18歳未満(18歳に達する日の属する年度まで。ただし、障害等級の1級または2級の障害の状態がある時は20歳まで)の子がいるときは、子の加算額があります。
3.特別障害給付金
令和5年度
障害基礎年金等級1級に該当する人・・・月額53,650円
障害基礎年金等級2級に該当する人・・・月額42,920円
対象は、国民年金への加入が任意であったが任意加入していなかった期間に生じた障害が、現在障害基礎年金の1級や2級相当の状態にある人です。国民年金への加入が任意だったのは、平成3年3月以前の学生、もしくは昭和61年3月以前に厚生年金などに加入していた人の配偶者期間です。
4.遺族基礎年金
令和5年度年額 795,000円(子の数に応じて加算があります。)
一家の働き手が亡くなられたときに、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に対して、子が18歳に達する日の年度末(1級や2級相当の障害がある場合は20歳)まで受け取ることができる年金です。
【年金が受けられる要件】
死亡した人はいずれかに該当していること。
- 国民年金の被保険者
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、国内に住所がある人。
- 保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある人で老齢基礎年金の受給権がある人。
1.または2.に該当する場合は、死亡した日の属する月の前々月までの期間のうち、保険料を納付した期間と免除された期間を合わせて3分の2以上あることが必要です。
ただし、令和8年3月末日までに亡くなった65歳未満の方については、直近1年間に保険料の未納がなければ要件を満たします(特例)。
5.寡婦年金
国民年金の第1号被保険者(任意加入者を含む)として国民年金の加入期間が10年以上(保険料納付済期間と免除期間を合わせて)ある夫が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに死亡した時に、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上で事実上の婚姻関係を含む)が60歳から65歳になるまでに受け取ることができる年金です。夫が受け取る予定だった老齢基礎年金額の4分の3の額が支払われます。
※ 平成29年7月31日以前に夫が死亡した場合、妻が寡婦年金を受給するための夫の国民年金の加入期間は25年です。
6.死亡一時金
国民年金の第1号被保険者(任意加入者を含む)の保険料納付済期間が36月(3年)以上ある人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに死亡した時、生計を同一にしていた遺族が受け取ることができます。
請求できる遺族の範囲や順位は、1 配偶者、2 子、3 父母、4 孫、5 祖父母、6 兄弟姉妹です。
※遺族基礎年金を受け取ることができる人がいる場合は、死亡一時金を受け取ることができません。
死亡一時金の支給額は、第1号被保険者として保険料を納めた月数に応じて決まっています。
| 第1号被保険者として保険料を納めた月数 | 支給額 |
|---|---|
| 36月以上180月未満 | 120,000円 |
| 180月以上240未満 | 145,000円 |
| 240月以上300未満 | 170,000円 |
| 300月以上360未満 | 220,000円 |
| 360月以上420未満 | 270,000円 |
| 420月以上 | 320,000円 |
付加保険料を36月以上納めている場合は、一律8,500円加算されます。
7.短期期在留外国人の脱退一時金
国民年金の納付済期間が6か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない外国人が、被保険者の資格を喪失し、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求すれば支給されます。一時金の金額は納付月数等で決まります。
5 年金を増やしたい人へ(任意加入、付加年金、国民年金基金)
1.任意加入
老齢基礎年金を満額(令和5年度年額795,000円)で受け取るためには、20歳以上60歳まで40年間保険料を納める必要があります。しかし、未加入や未納の期間などがあると、期間に応じて老齢基礎年金が減額されます。老齢基礎年金の満額受給や、増額を希望される場合は、届出により国民年金に任意で加入することができます。保険料の納付は原則として口座振替になります。
付加年金をあわせて納めていただくと、より増額させることができます。
【未加入の例】
昭和61年3月以前に会社員等(厚生年金、共済組合加入者)の配偶者として扶養されていた期間や、平成3年3月以前の学生期間は、国民年金の加入が任意でした。この間、国民年金に未加入であった場合は、満額で受け取ることができません。
【対象者】
- 海外に住んでいる(20歳以上65歳未満)の日本人
- 老齢基礎年金を満額に近づけたい人(老齢基礎年金を受けていない60歳以上65歳未満)
【注意事項】- 加入は届出された日からとなり、その月の保険料から納めることになります。また、やめるときは、届出が必要です。
- 40年(480月)を越えて保険料を納付することはできません。
- 厚生年金などに加入中の人は加入できません。
- 老齢基礎年金を繰上げて受給している人は、加入できません。
- 保険料の免除申請はできません。
- 納めた保険料は、全額社会保険料控除の対象になります。
- 65歳に達しても10年の受給資格期間(平成29年8月から)を満たさない昭和40年4月1日以前生まれの人は、最長70歳まで任意加入できます。
2.付加年金
付加保険料400円を毎月の定額保険料(令和5年度 16,520円)とあわせて納めることで、納めた金額の半分が、老齢基礎年金の年額に上乗せして支払われます。2年間受給すると、納めた保険料と同額になりますので、3年目からはお得です。申込みできる人は、国民年金1号被保険者と任意加入者で、加入した月の分から納めることになります。
| 加入年数 | 保険料納付額 | 付加年金受取額(年額) | 2年間で受け取る付加年金額 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 4,800円 | 2,400円 | 4,800円 |
| 10年 | 48,000円 | 24,000円 | 48,000円 |
| 40年 | 192,000円 | 96,000円 | 192,000円 |
注意事項
- 保険料は、納付期限(翌月末日)を過ぎても2年間は納めることができます(平成26年4月分以降に限る)。また、やめたい時は届出が必要です。
- 第3号被保険者(厚生年金などに加入している人に扶養されている配偶者)、厚生年金などに加入している人、国民年金基金に加入している人は、お申し込みできません。
- 老齢基礎年金を繰り上げした場合減額されます。
- 納めた保険料は、全額社会保険料控除の対象になります。
3.国民年金基金
自営業・フリーランスなどの人のため、より充実した老後を送れるよう、老齢基礎年金に上乗せして年金をお支払いする制度です。国民年金の第1号被保険者と60歳以上65歳未満や海外居住者で任意加入している人が加入できます。 掛金は、加入時の年齢、性別、給付の型と口数によって決まります。なお、国民年金基金と付加年金の両方に加入することはできません。
詳しくは、国民年金基金へお問い合わせください。
日本年金機構ホームページ<外部リンク>
6 マイナポータルを利用した国民年金に関する電子申請
令和4年5月からマイナポータルを利用した国民年金に関する電子申請が始まりました。
1 対象となる手続き
・国民年金への加入・種別変更の届出(退職後の厚生年金からの変更等)
・国民年金保険料の免除・納付猶予の申請
・国民年金保険料の学生納付特例の申請
2 手続き先
マイナポータル<外部リンク>
マイナポータルのトップ画面から以下の手順で希望する手続きをお選びください。「メニュー⇒手続の検索・電子申請⇒年金関連の手続⇒希望する手続を選択する」
3 問い合わせ先
ねんきん加入者ダイヤル(☎0570-003-004)
050から始まる電話でおかけになる場合は(☎03-6630-2525)
7 公的年金シミュレーター(試験運用中)<外部リンク>
将来受け取れる年金額を試算できるツールとして厚生労働省が公開しています。ID・パスワードは不要で、すぐに試算を始めることができます。また、「ねんきん定期便」の二次元コードを利用すれば、より簡単な入力も可能です。