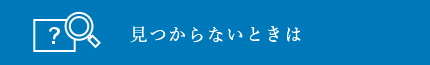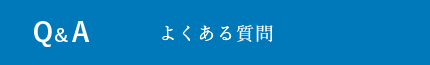本文
国民健康保険の給付
病気になったり、ケガをしたときは、医療機関に被保険者証を提示して受診してください。
給付を受けられない場合
被保険者証を持っていても、次の場合には保険給付を受けられなかったり、制限されることがあります。
- 保険適用外のもの
保険のきかない診療、健康診断、人間ドック、予防注射、正常な妊娠や分娩、歯列矯正、美容整形等 - 業務上のケガや病気
労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇主の負担となります。 - 故意の犯罪行為や疾病負傷、ケンカや飲酒運転などによる交通事故等
交通事故の被害者の場合は、国保で一旦立替払いを行い、治療が受けることができる場合があります。詳しくはこちらをクリックしてください。 - 医師や保険者の指示に従わなかったとき
傷病手当金
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、国民健康保険の被保険者のうち、被用者(雇用されている人。賃金を受け取って労働に従事する人。)で、新型コロナウイルスに感染(発熱等の症状があり感染が疑われる人も含む)し、療養のため一定期間仕事を休んだことにより給与等が支払われなかった方等を対象として、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望される場合には、事前に電話でご相談ください。
支給対象者
大船渡市国民健康保険の被保険者である被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日がある人
支給額
1日当たりの支給額×支給対象日数
※支給額には上限があります。
○1日当たりの支給額
直近3か月間の平均給与日額(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3
○支給対象となる日数
・3日間連続して休んだ後、4日目以降の仕事に就けなかった日数
※4日目以降は、無給もしくは平均給与日額の2/3未満の給与支払いがされた日数。
※勤務を予定していた日数。
支給対象期間
支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のために労務に服することができない期間
(ただし、支給を始めた日から1年6か月が上限です。)
※労務を服することができなかった日ごとに、その翌日から2年を経過すると、時効により傷病手当金の請求権は消滅します。
申請方法
以下の1から4の申請書をご記入のうえ、1から7を国保医療課国保年金係へお持ちください。
※ 郵送による手続きをご希望の場合は、以下の1から4の申請書をご記入の上、5~
7の写しを同封し、 国保医療課国保年金係まで送付してください。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(その1世帯主記入用) [Excelファイル/26KB]
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(その2被保険者記入用) [Excelファイル/37KB]
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(その3事業主記入用) [Excelファイル/44KB]
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(その4医療機関記入用) [Excelファイル/35KB]
- 被保険者証
- 通帳等の振込先口座がわかるもの
- 申請人の本人確認書類
- 【記入例】国民健康保険傷病支給申請書(その1世帯主記入用) [Excelファイル/28KB]
- 【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(その2被保険者記入用) [Excelファイル/37KB]
- 【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(その3事業主記入用) [Excelファイル/61KB]
- 【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(その4医療機関記入用) [Excelファイル/38KB]
高額療養費
世帯の1か月間の医療費の自己負担額が、その世帯の自己負担限度額を超えた場合、申請すると超えた分が高額療養費として支給されます。(自己負担限度額は世帯の所得状況に応じて、分かれています)
70歳未満の方
| 区分 | 自己負担限度額(月額) | (4回目以降) | |
|---|---|---|---|
| ア 旧ただし書所得 901万超 |
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1パーセント | 140,100円 | |
| イ 旧ただし書所得 600万超901万円以下 |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1パーセント | 93,000円 | |
| ウ 旧ただし書所得 210万超600万円以下 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1パーセント | 44,400円 | |
| エ 旧ただし書所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 | |
| オ 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | |
- 旧ただし書所得とは総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額です。
- 4回目以降とは、多数該当のことで、12か月以内に4回以上高額療養費に該当している場合の4回目以降の自己負担限度額です。
70歳未満の方の計算方法
- 月ごとの受診について1か月単位で計算します。
- 同じ医療機関でも医科と歯科、入院と外来は別々に計算します。
- 調剤薬局の一部負担金は、処方箋を発行した医療機関の一部負担金と合わせて1つとして計算します。
- 加入者それぞれが、同一月内に1医療機関あたりの一部負担金が21,000円以上を超えるものが計算対象となります。
- 入院時の部屋代、食事代、病衣代等は保険適用外のため、計算に含めません。
70歳以上の方
| 区分 | 自己負担限度額(月額) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来 (個人ごとに計算) |
入院+外来 (世帯単位) |
|||||
| 現役並み所得者 | 課税所得 690万円 以上 |
現役並みIII | 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% (4回目以降 140,100円) |
|||
| 課税所得 380万円以上 690万円未満 |
現役並みII | 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% (4回目以降 93,000円) |
||||
| 課税所得 145万円以上 380万円未満 |
現役並みI | 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% (4回目以降 44,400円) |
||||
| 一般 | 18,000円 (年間上限※ 144,000円) |
57,600円 (4回目以降 44,400円) |
||||
| 低所得者 | 区分II | 8,000円 | 24,600円 | |||
| 区分I | 8,000円 | 15,000円 | ||||
※年間上限とは8月から翌年7月までの1年間
- 低所得者区分IIとは、住民税非課税の人(低所得者区分I以外の方)です。
- 低所得者区分Iとは、住民税非課税の世帯員の各所得が必要経費及び控除(年金所得の控除額は80万円)を差し引いたときに0円となる方です。
- 4回目以降とは、多数該当のことで、12か月以内に4回以上高額療養費に該当している場合の4回目以降の自己負担限度額です。
70歳以上の方の計算方法
- 月ごとの受診について、医療機関や診療科の区別なく合算して計算します。
- 入院時の部屋代、食事代、病衣代等は保険適用外のため、計算に含めません。
申請方法
申請時期
診療を受けた月からおおむね3か月後に、該当する世帯の世帯主あてに、市役所から「高額療養費支給のお知らせ」が届きますので、申請してください。
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書(市役所からお送りした申請書)
- 領収書(原本)
- 通帳等の振込先口座がわかるもの
- マイナンバーがわかるもの
- 申請人の本人確認書類
- 委任状 [Wordファイル/19KB](別世帯の方が申請、または世帯主以外の方が代理受領する場合のみ)
療養費
次のような場合は、いったん全額負担となりますが、申請により自己負担額を超える額があとから支給されます。
- 急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに医療機関を受診したとき
- 医師が必要と認めた場合で、コルセットなどの補装具をつくったとき
- 医師の同意により、針、灸、マッサージの施術を受けたとき
- 手術などで生血を輸血したときの費用で医師が認めたとき
- 海外渡航中に急病などで治療を受けたとき
1.急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに医療機関で受診したとき
申請に必要なもの
- 国民健康保険療養費支給申請書 [Wordファイル/28KB]
- 領収書(原本)
- 診療報酬明細書
- 通帳等の振込先口座がわかるもの
- マイナンバーがわかるもの
- 申請人の本人確認書類
- 委任状 [Wordファイル/19KB](別世帯の方が申請、または世帯主以外の方が代理受領する場合のみ)
2.医師が必要と認めた場合で、コルセットなどの補装具をつくったとき
申請に必要なもの
- 国民健康保険療養費支給申請書 [Wordファイル/28KB]
- 医師が必要と認めた診断書
- 領収書(原本)
- 靴型装具を作成した場合、装具の写真
- 通帳等の振込先口座がわかるもの
- マイナンバーがわかるもの
- 申請人の本人確認書類
- 委任状 [Wordファイル/19KB](別世帯の方が申請、または世帯主以外の方が代理受領する場合のみ)
※療養費の申請は、医療機関等への支払いから2年を過ぎると時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
訪問看護療養費
医師が在宅で医療を受ける必要があると認め、訪問看護ステーションを利用した場合、費用の一部を支払うだけで残りは国保が負担します。
被保険者証を訪問看護ステーションなどに提示してください。
入院時食事療養費
入院した場合の食事代は下表のとおりです。住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、下記の金額が適用されます。
| 区分 | 食事代(1食あたり) | ||
|---|---|---|---|
| ~R6.5.31 | R6.6.1~ | ||
| 一般(住民税課税世帯) | 460円※ | 490円※ | |
| 住民税非課税世帯 | 過去12か月の入院日数が90日以下 | 210円 | 230円 |
| 過去12か月の入院日数が90日以上(長期入院該当) | 160円 | 180円 | |
| 区分 | 食事代(1食あたり) | |||
|---|---|---|---|---|
| ~R6.5.31 | R6.6.1~ | |||
| 現役並み所得者、一般(住民税課税世帯) | 460円※ | 490円※ | ||
| 住民税非課税世帯 | 低所得II | 過去12か月の入院日数が90日以下 | 210円 | 230円 |
| 過去12か月の入院日数が90日以上(長期入院該当) | 160円 | 180円 | ||
|
低所得I(世帯主及び国保加入者全員が所得0円 |
100円 | 110円 | ||
※指定難病患者、小児慢性特定疾病患者等は280円になります(令和6年5月31日までは260円)。
減額認定証の申請に必要なもの
- 認定を受けようとする方の被保険者証
- 過去12か月の間に市民税非課税の期間で入院日数が90日を超える場合、その確認ができる領収書(原本)
- マイナンバーがわかるもの
- 申請人の本人確認書類
- 委任状 [Wordファイル/19KB](別世帯の方が申請する場合のみ)
標準負担額差額支給申請
やむを得ず減額認定証の提示ができずに、減額されていない食事代を支払ったときは、申請すると差額分の払い戻しが受けられます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険標準負担額差額支給申請書 [Wordファイル/21KB]
- 領収書(原本)
- 通帳等の振込先口座がわかるもの
- マイナンバーがわかるもの
- 申請人の本人確認書類
- 委任状 [Wordファイル/19KB](別世帯の方が申請、または世帯主以外の方が代理受領する場合のみ)
出産育児一時金
大船渡市国保に加入している方が出産したとき、申請により、その世帯の世帯主に出産育児一時金が支給されます。
また、出産にかかった費用を国保が直接、医療機関等に支払う「直接支払制度」を利用することにより、出産育児一時金は国保から直接医療機関等に支払われますので、医療機関等での支払いは、出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額になります。
支給金額
出産日が令和5年4月1日以降の場合
| 区分 | 支給額 | ||
|---|---|---|---|
| 妊娠第22週以降の出産(死産、流産を含む) | 産科医療補償制度(※)に加入する医療機関等の医学的管理下における出産 | 50万円 | |
| 産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産 | 48万8千円 | ||
| 妊娠12週以上21週目までの出産(流産等を含む) | 48万8千円 | ||
出産日が令和5年3月31日以前の場合
| 区分 | 支給額 | ||
|---|---|---|---|
| 妊娠第22週以降の出産(死産、流産を含む) | 産科医療補償制度(※)に加入する医療機関等の医学的管理下における出産 | 42万円 | |
| 産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産 | 40万8千円 | ||
| 妊娠12週以上21週目までの出産(流産等を含む) | 40万8千円 | ||
※産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺となった赤ちゃんに対する補償制度で、妊婦さんが安心して出産できるよう医療機関が加入する制度です。この制度には、全国ほぼすべての医療機関が加入しています。
申請方法
大船渡市国保に加入している方が直接支払制度を利用する場合は、医療機関等での申し込みとなり、国保医療課窓口への申請は不要となります。
ただし、
- 直接支払制度の利用を希望しない
- 出産費用が出産育児一時金の支給額未満となり、差額が発生した
- 国外での出産
上記いずれかに該当する場合は国保医療課窓口への申請が必要となります。
申請に必要なもの
- 出産一時金支給申請書 [Wordファイル/19KB]
- 医療機関等の領収書
- 医療機関から交付される直接支払に関する合意文書(合意文書とは、被保険者が病院等で直接支払制度の利用の有無を表す文書で、入院または出産の際に病院と取り交わすことになる書類です。詳しくは医療機関等にご確認ください。)
- 出産した方の被保険者証
- 通帳等の振込先口座がわかるもの
- マイナンバーがわかるもの
- 申請人の本人確認書類
葬祭費
大船渡市国保に加入している方が亡くなられたときは、申請により葬儀を行った喪主の方に、葬祭費として3万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 葬祭費支給申請書 [Wordファイル/19KB]
- 申請人(喪主)の通帳等の振込先口座がわかるもの
- マイナンバーがわかるもの
- 申請人の本人確認書類
移送費
病気やケガなどにより移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要があって移送された場合、移送にかかった費用を国保が必要と認めた場合に支給します。
支給要件
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 患者が療養の原因である病気やけがにより移動が困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
上記3つの条件のいずれにも該当すると認められた場合に支給されます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険移送費申請書 [Wordファイル/19KB]
- 医師の意見書
- 移送にかかった費用の領収書(原本)
- 通帳等の振込先口座がわかるもの
- マイナンバーがわかるもの
- 申請人の本人確認書類
支給対象外の例
- 家族及び病院の都合による転院の場合
- 単に通院のため交通機関を利用したときの運賃 など
特定疾病療養受療証
次の疾病の場合に、医師の診断に基づいて交付されます。
- 人工透析を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害または先天性血液凝固第IX因子障害(血友病)
- 抗ウィルス剤を投与している先天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣が定める者に限る)
自己負担額
1万円
- 70歳以下で人工透析を実施している慢性腎不全の人のうち、上位所得者と判定される人の自己負担限度額は2万円となります。
- 慢性腎不全の人で市県民税の申告のない人のいる世帯の人は、所得判定が出来ないため上位所得者とみなされます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険特定疾病認定申請書 [Wordファイル/19KB](医療機関から証明を受けたものに限る)
- 認定を受けようとする方の被保険者証
- マイナンバーがわかるもの
- 申請人の本人確認書類
- 委任状 [Wordファイル/19KB](別世帯の方が申請する場合のみ)