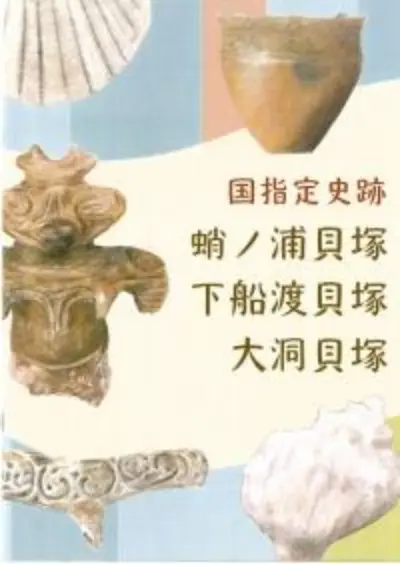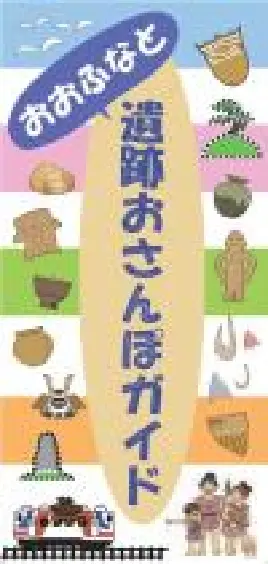大船渡市の美しい風土には、大地の悠久の営みが刻まれています。
また、縄文時代以来、彩り豊かな文化が開花し、今も貝塚、仏像、民俗芸能、年中行事などとして見ることができます。市内には89件の指定文化財(国指定9件、県指定12件、市指定68件)と195件の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)があり、地域の歴史と文化、自然を今に伝えています。
自然

傾きの謎を知る 碁石海岸
国指定名勝及び天然記念物
切り立った断崖に、波間に突き出した岩々。絶景が広がる碁石海岸には、ダイナミックな地球のドラマが秘められています。紐解くカギは、岩肌に現れた斜めの縞模様。その正体は、およそ1億3000万年前に堆積した地層です。なぜ斜めに傾いているのでしょうか?
碁石海岸の岩石は、海底にあった地層が押し上げられたものです。斜めの地層は、巨大な力で大地が変形したことを物語っています。隆起した大地は、長い年月をかけて波や風に削られ、雄大な海岸美を生み出しました。巨大な岩にぽっかりと穴が空いた「穴通磯」は、荒波が創り出した自然のアート。迫力満点の「乱曝谷」や、波が岩を打つたびに響き渡る「雷岩」など、見どころ満載!時空を超えて太古の地球に思いを馳せるひとときを過ごしてみませんか?

4億5000万年の聖地 樋口沢ゴトランド紀化石産地
国指定天然記念物
かつて、日本には4億年以上前の古生代の地層は存在しないと考えられていました。その常識を覆したのは、大船渡市の樋口沢です。
東北大学の学生だった小貫義男氏は、卒業論文の研究のため、この地を調査していました。ある日、樋口沢の石に腰を下ろして一休みしているうちに、疲れからうとうとと眠ってしまいます。目を覚ますと、ふと近くの石灰岩に刻まれた化石に気づきました。それこそが、日本で初めて確認された古生代シルル紀のサンゴの化石だったのです。
さらに樋口沢を奥へ進むと、約4億5000万年前から2億5000万年前までの古生代の地層が広がります。たった1本の道を歩くだけで、気が遠くなるような地球の歴史をたどることができるのです。日本全国を探しても、このような場所は他にはなく、まさに唯一無二の“地球のタイムトンネル”とも言える場所です。

新種の宝庫 化石の王様 三葉虫
大船渡の長安寺、大森、と聞いて三葉虫を思い浮かべる人は、相当の化石好きです。
今は絶滅し、化石でしかその姿を知ることができない三葉虫。2万を超える種類がいたとされ、「化石の王様」と呼ばれています。そんな三葉虫の一大産地が大船渡だということを知る人は少なく、大船渡市日頃市町の長安寺や大森では、三葉虫の新種が見つかっており、学名に地名がつけられています。
日本で一番多くの三葉虫が見つかる土地である大船渡。私たちの足元には、まだ見ぬ新種の三葉虫が眠っているのかもしれません。
文化

大船渡初の石灰岩利用者? 関谷洞窟住居跡
岩手県指定史跡
資源が少ないと言われる日本において、国内自給率100%の石灰岩。その貴重な資源は、セメントの材料として活用され、地域の発展を支えています。
この石灰岩を最初に利用したのは、縄文人でした。長い年月をかけ、石灰岩の地層に水が流れて空洞となり、洞窟ができます。その洞窟を住処として利用したのが、関谷洞窟の縄文人です。洞窟の内部は、雨風をしのぐことができ、夏は涼しく、冬は暖かい。人々には、天然の空調が心地よい理想的な環境だったことでしょう。洞窟内部からは、煮炊きに使った土器や石器、石灰岩の成分のおかげで分解されずに残った獣骨などが出土し、当時の暮らしが垣間見えます。
洞窟は、小規模な鍾乳石がある鍾乳洞で、光を当てるとキラキラと光る岩肌や、奥深くにには地底湖があり、大規模な洞窟であることがわかっています。

今も昔も水産のまち 大洞貝塚
国指定史跡
マグロにタイにウニにサケ…。これは、大船渡の縄文人が食べていた魚介類です。どうしてわかるのか?ズバリ!「貝塚」というタイムカプセルを発掘調査することで、縄文人の食事のなかみがわかり、周辺の自然環境もわかるのです!
貝塚では、魚の骨や貝殻がたくさん見つかります。その豊かさは現代の食卓にも引けを取りません。どうやって縄文人はこれらの海の幸を手に入れていたのでしょうか?その答えは、大洞貝塚が教えてくれます。
大洞貝塚では、鹿の角から作られた小さなツリバリや、突き刺さると抜けづらいモリなど、工夫を重ねた漁の道具が発見されました。数千年後を生きる私たちも驚くような技と知恵の結晶です。縄文時代の大船渡にも、腕のいい漁師たちがいたのです。

博物館のアイドル 細浦上ノ山貝塚の土偶
大船渡市末崎町の細浦上ノ山貝塚から出土したと伝わる土偶は、その愛らしい姿で多くの人を魅了しています。まるい目とふっくらしたフォルム、まるで縄文時代からやってきたアイドルのよう。
約4,000年前、この地に暮らした縄文人たちは、豊かな海と森に囲まれながら生活を営んでいました。土偶は、当時の人々が安産などの祈りを込めてつくったと考えられています。
縄文の祈りが込められた土偶を通して、はるか昔の暮らしに思いを馳せてみませんか?大船渡市立博物館で、縄文の小さなアイドルがあなたを待っています。

ナマケモノ集合! 吉浜のスネカ
ユネスコ無形文化遺産、国指定無形民俗文化財
1月15日の夜、「グオッグオッ」と鼻を鳴らし、玄関の戸をガタガタと鳴らす音が聞こえたら、やってきた合図です。この突然の来訪者は、戸を開け放つと、大声で叫びます。「カバネヤミはいねぇがぁ?」新たな一年の訪れを告げる「スネカ」の到来です。
「カバネヤミ」とは、囲炉裏の火にあたってばかりいるような怠け者のことです。そんな怠け者の火ダコができた「すねの皮」をはぎとる「スネカワタクリ」が、「スネカ」の語源になったと言われています。
200年以上も前から続いてきた恐ろしい「スネカ」は、子どもの健やかな成長を願い、豊作や福をもたらしにやってくる「来訪神」でもあります。その伝統は、今もこの地で、大切な地域の宝として受け継がれています。
関連情報
国指定史跡 蛸ノ浦貝塚 下船渡貝塚 大洞貝塚
国指定史跡 大洞貝塚
おおふなと遺跡おさんぽガイド
その他
文化財は、地域の歴史・文化・自然を理解するために欠かせない存在であり、未来を創る礎となる公共の財産です。より多くの方々に地域の文化財を知っていただき、協力して守り伝えていくことが大切です。
文化財の所在地や所有者を変更する場合や、史跡・名勝・天然記念物の指定区域内で工事などを実施する場合には、事前に計画を提出して許可を得る必要があります。必要となる手続きは文化財の種類によって異なります。詳しくは下記までお問い合わせください。